国立大学法人 東京農工大学/村田研究室
|
|
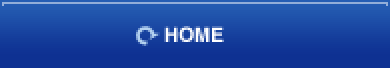 |
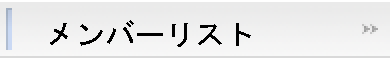 |
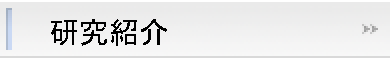 |
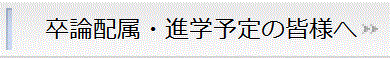 |
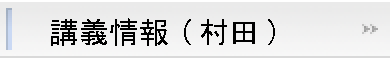 |
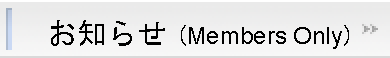 |
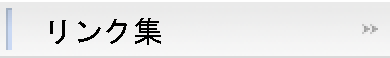 |
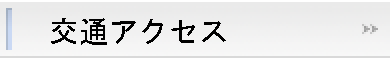 |
|
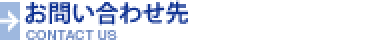 |
国立大学法人
東京農工大学 大学院 工学府
機械システム工学専攻
熱流体システム設計分野
村田研究室 |
|
Tokyo University
of Agriculture and Technology
Thermal Fluids Engineering Lab.,
Dept. of Mechanical Systems Engineering
Murata Lab. |
〒184-8588
東京都小金井市中町2-24-16
[MAIL]
webadmin
[AtMark]mmlab.mech.tuat.ac.jp
|
|
|
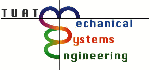 |
|
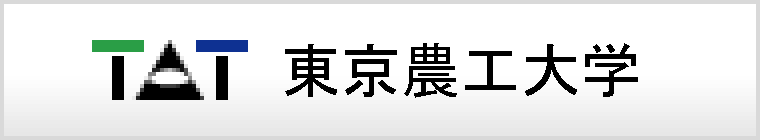 |
|
|
用語説明
乱流 流速が高くなると流れは自然に乱れて,大きな拡散・混合作用を持つよう
になります.伝熱にとっては大きな混合作用はより多くの熱を伝えてくれるのでプラスなのですが,同時に流体の運動量もすばやく伝わるために流体を流すのに
必要な圧力差を大きくする必要が生じます.
Large
Eddy
Simulation(LES) 乱流による拡散・混合効果をモデル化する一手法です.Reynolds平均乱流モデルではアン
サンブル平均(実際はある時間幅での時間平均)を施した場から見た乱流輸送をReynolds応力として表現します.一方LESでは数値計算する際の空間
格子幅で空間平均を施した場から見た格子解像度以下の成分による乱流輸送についてだけモデル化します.他の成分については時間・空間変動を再現しますので
乱流モデルの影響を最小限に抑えることができ,複雑乱流に対しても実際の物理現象を再現できます.
流れの可視化 空気や水といった流体は無色透明なので,流体のどの部
分が速く流れているかはわかりません.そこで色素や粒子を流れに注入し,それらをマーカー(目印)にして流れの様子を調べることを「流れの可視化」と呼び
ます.
画像処理流速計(PIV/PTV) トレーサー粒子(または他のマーカー)を用いた流れの可視化画像内のある検査小領域が次の時刻にどこに移動したかを検
査小領域内の模様(粒子配置)から探索して,速度ベクトルを算出する流速計のこと.粒子一つひとつの位置を追跡していく方法もあります.
並列計算
熱流体現象の数値解析は,基礎式である偏微分方程式を離散化して連立方程式を解く問題に帰着します.計算領域が大きくなると必要な演算量も増え,計算時間
や記憶領域が膨大になります.そこでお互いに接続された複数の演算装置(CPU)に計算を割り振ることで,計算時間と記憶領域を小さくするのが並列計算で
す.通常の1CPUでの計算に比べて異なるCPU間での通信や同期待ちなどの余分な時間がかかるので,N個のCPUを用いたからといって計算時間が1/N
になるわけではありません.
非定常法
ある時刻の固体表面温度計測結果から半無限固体内一次元熱伝導問題の理論解
を用いて熱伝達率を算出する方法.
古典分子動力学法 我々が連続体として取り扱っている流体もミク
ロに見れば,離散的な分子から構成されています.この分子1つ1つのNewtonの運動方程式を解くことで系の状態を再現する数値解析手法を分子動力学法
と呼びます.「古典」と頭についているのは,分子間ポテンシャルとして経験的な関数を用いていることを表します.分子間力は分子間ポテンシャルを微分して
求めることが出来ます.
量子分子動力学法(第一原理分子動力学法)
「量子」と頭についているのは,分子間ポテンシャルとして経験的な関数を用いずに,原子核まわりの電子の挙動をシュレディンガーの波動方程式から求め,量
子力学的に忠実に解析することを表します.但し,実際には多電子状態での電子間相関や電子スピンの扱いに経験的な取り扱い(モデル)を含みます.
|

